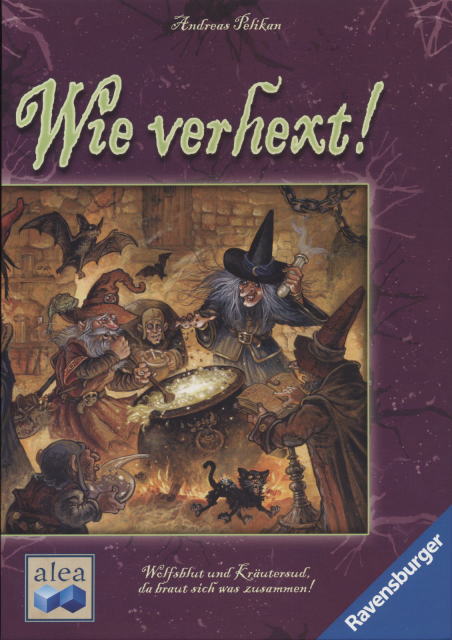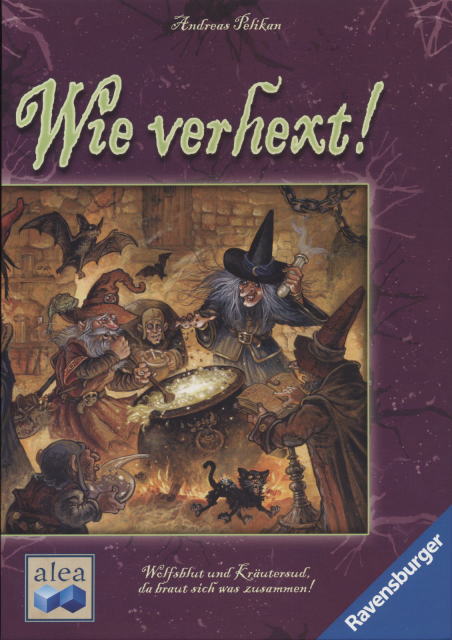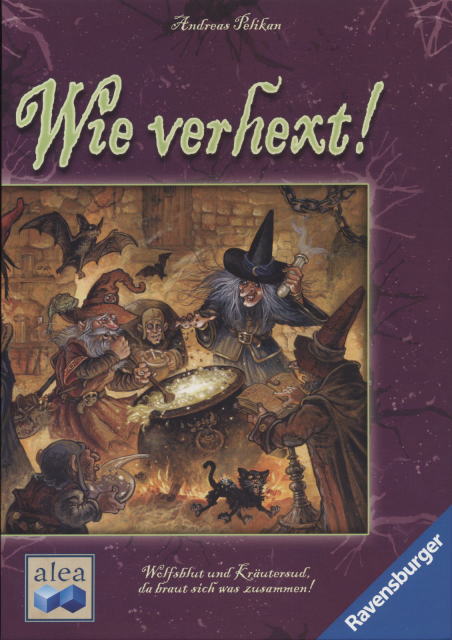 |
Andreas Pelikan
|
alea
|
3〜5人
60分
|
魔法にかかったみたい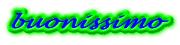
ヒヒヒヒ、ここに蛇の毒をぽとりぽとりと2滴垂らすのじゃ。
ほら、そうすれば、どんな美しい姫をも化け物のような姿にする薬が完成じゃ。
これを使うかどうかはおぬし次第じゃぞ。ヒヒヒ。
プレイ感
2008年度ドイツゲーム大賞ノミネート作品の中で、やたらと評判が高い。ゲーマー向けブランドaleaが果たしてドイツゲーム大賞を受賞するか、mia、コツミ、Jyama、OECの5人にてやってみた。
変則的なマストフォローのトリックテイクで、全員が12枚の同じカードを持ち、その中からラウンドに使用する5枚を密かに選び出す。で、リードプレイヤーがカードを出すと、時計回りに同じカードがあれば必ず出すのだ。持ってない場合は、パスで今回は関係なくなる。で、持ってる人はカードを出し、権利を奪うか、支持するかを宣言する。支持すると権利をフルで行うよりグレードダウンした形でアクション可能だが、権利を奪うと、後ろのプレイヤーが同じカードを持ってて権利を奪うと宣言したら、まったくアクションが出来なくなるのだ。
アクションというのは、魔法の薬を作るに必要な材料を集めたり、それを使って魔法の薬を作ったり(いわゆる勝利ポイントが入る)するのがテキストに書かれている。最初は材料集め、材料が集まれば魔法の薬を鍋に放り込むアクションを選べばいい。

蛇の毒、狼の血、薬草が基本的な材料。例えば直近で出したカードは、アクションの実行なら金貨を好きな材料3つにするが、支持に回ると材料1つにする事が出来る。上に並んでるカード群は左から金の徴税、材料の徴税、魔法、鍋とならんでおり、右下に勝利ポイントが描いてある。徴税カード2種類は上に描いてる数が集まれば勝利点として手に入れる事が出来るカード。
そういう風に皆に説明したが、実際にやってみるとなかなか難しいようだ。まずは3種類ある材料集めだが、これだけで3種類のカードが決まってしまう。残りの2種類をなんにするかが難しいのだ。3種類の材料集めカードは、皆が選ぶのを解っていても選ばざるを得ない感があるのがちょっとネックだ。そうなると最初の手番は非常に不利である。リードプレイヤーは、”支持”出来ないからだ。

最初はこのように5枚のカードを選択。色によって手に入るカードが解るようになっている。金色は金貨に関するカード、青色は材料を鍋にぶち込んで勝利点にするカードだ。材料が揃いに揃ってるので、鍋カードを3枚とも入れてみた。
わし「まむしドリンクを貰う」
Jyama「じゃあ、支持します」
mia「わたしも支持」
コツミ「持ってる…よなあ。支持」
OEC「アクションで!」
こうなるとリードプレイヤーは損で、周りは少なくとも蛇の毒を1つは貰えるのにわしだけ0個だ。
次に、OECからのカードで、野菜ジュースとタバスコをわしも支持してようやく1つずつ貰う事に成功。
こうして、材料を少しだけ入手する中、OECがこっそり別のカードを混ぜてくる。
OEC「クレクレ君カードです」
クレクレ君カードとは、徴税のカードで、相手が持っているお金や材料を徴税し、それを勝利点となるカードに変換する他力本願なカードである。
しかし、こんなカードがあったのかと、全員すっかりOECのクレクレ君カード攻撃にやられてしまう。
OEC「やった」
むむむ! さすが、国立大学出だけあるぜ。
わし「わしら、阿呆やから、なんか見事にやられてんな」
Jyama「ほんまですねえ」
その後も、見事にクレクレ君カードを織り交ぜてOEC見事に得点を重ねていく。

鍋カードは、アクションが成功すると材料を描いてある通り払わないと手に入らない。最初は、1個くらいで手に入るのだが、徐々に赤2白1みたいに複合材料となってくる。もちろん勝利点も高くなってくる。また鍋カードを手に入れる時に、1つだけ追加で材料を払う事で小瓶が手に入る。これも勝利点1となるので、是非毎回手に入れたいところだ。
こりゃあ、負けたな。
なんといってもOECがわしの右となりってのが痛い。わしが頑張れば、奴は一番おいしいラスプレイヤーになるのだ。このゲーム、構造的にラスプレイヤーが一番強いのが解るだろう。最後に「強奪する」って言えば終いなのだ。
わし「論入のおっさん、頑張ってリードプレイヤーなってくれやあ」
Jyama「上手くいかんです」
※説明しよう。Jyamaはわしの大学の後輩であり、尚かつ日本語さえ書ければ誰でも入れるんちゃうかと言われる悪名高き論文入試で入った男だ。わしらが朝からお受験しとるのに、こやつらは、昼からだらっときて論文1つ書いて、さっと帰るだけで合格したのだ。この悪名高き論入は既になくなったらしい。

手に入れた鍋カードは裏向きに伏せ(小瓶もその下に入れておく)て、現在の得点を解らなくするが、カラスの絵のカードはゲーム終了条件に関係してくるのでオープンにしておかなければならない。
こうなっては、敵は完全にOECひとり。だが、わしが頑張ってアクションを行うと常に奴が利するのだ。
※アクションを行った者が次のリードプレイヤーとなる。
ところどころ、順番がまだなのに「パス」宣言をしてルール違反を連発するmiaを尻目に、ゲームは中盤へとさしかかる。
※このゲームの肝はそのカードを順番に持ってるかどうかを判定する事なので、時計回りの順番通りに宣言しなければシステム自体が壊れる。
OECひとつ手前のコツミも「持ってるんかなあ?」と顔をのぞき込むが、初めて会った人を前にして極度の緊張のため、自然にポーカーフェイスとなったOECを読み取れず。
さらには、ラスプレイヤーにも関わらず、わざと支持宣言をしてわしをリードプレイヤーのままにする国立殺法の前に、私大一般入試と論入コンビはたじたじ。
それでも相手が持っている材料を見届けて、上手く裏をかいて材料を少しずつ集めては、鍋にぶち込んでは勝利点を稼ぐわし。
なんかやたらとリードプレイヤーになって非常に苦しい展開。
得点カードにカラスが描かれているカードがあり、これが4枚以上出た時点で最終ラウンドなのだが、3枚既に出ており、これこそ最終やなと思ってカードを選択したら、誰も獲得しなくて次ラウンドに持ち越した時は痛恨。材料を集めておくべきところが、終わりと思って勝利点を少しでも稼げるカードを選んでしまった。
わし「意外と持つなあ」
Jyama「そうですねえ」
密かに次のラウンドでも終わらんのとちゃうかと思って、こっそり材料を手に入れる作戦にでた。これが功を奏して、そのラウンドでも終わらず、次のラウンドでわしがそのカラスの得点カードを手に入れて最終ラウンドとした。
ただ、OECの再びやらしい国立プレイにあい、わしが狙っていた高得点の方のカードを取る前に安い方の得点で材料を使わされてしまったのが心残り。

最終得点。材料を4つ余らせてしまった。右上にあるのが小瓶である。
ぼろ負けやなあと思って、勝利点を計算したら、なんとわしが勝ってた。
所要時間80分 本来ならさくっと終わるらしいが、ルール確認しながらと初心者を混ぜたので時間がかかってしまったようだ。
うーん、なんでやろと思ったら、わしゃ考えたらリードプレイヤーとなったのが多かったので、普通に有利に進めてたようだ。またOECは、前半は得点を重ねてたけど後半はあまり得点出来なかったらしい。
OECのコメント
相手が何をしたいかを考えるよりも、相手が何をしないかを考えるのが新鮮に感じた。
見た目とルール以上に重いプレイ感だったけど個人的には好み。
効率の良い物々交換を軸に展開する必要があるんだけども、ラスト手前のラウンドに完全に読みを外してしまったのが痛恨で、2位。
ルールはいいけど、ちょっとカードの効果に雑な印象を持った。
ネーミングはともかく(笑)もう少し安ければ買ってもいいんだけどなぁ〜
miaのコメント
難しかった。カードの絵も分りにくくて。
ソマーリオ
得点の集め方の構造は、フィストオブドラゴンストーンに似ている。材料を集めるカードを出して、ある程度揃うと、その材料を勝利点に変えるカードを使う。
カードの絵の解りにくさや、テキストのある魔法カードのおかげでなんだか非常に難しく感じた。また、あれこれ考えるとプレイテンポも悪くなり、なんでこれが皆が絶賛するのか解らない。まだ1度目のプレイだからだと思うが、ドイツゲーム大賞という事を考えると、どう考えてもこれはゲーマー向けのゲームに感じられるので受賞は難しいように思えるのだが。
初心者がさっと入れるタイプのゲームには思えなかったのだ。さすがはaleaである、とむしろ言いたい。(ただ初心者でも楽しめるという話も聞くので、単にわしがヘボいのかもw)
今回のメンバーが初心者クラスが二人いたのと、5人プレイの難しさというのもあり、「してやったり!」とか「読まれた!」みたいなゲームの肝が感じにくかったのも評価を下げている。普通かな。miaもそうだがこれならストーンエイジの方が今の印象ではおもろく感じる。本命のズライカの入手がまだなので(おそらく発表に間に合わないだろうが)、次点の予想は魔法にかかったみたいではなく、ストーンエイジとしたい。
わしらが下手なのかは知らないが、フィストオブドラゴンストーンのような激しい読み合いがなかったように思う。カードゲームの癖にやたらとルールがややこしいなというのが本音だ。ただこのゲームの真価は、カードの効果に慣れてきた2回目3回目のように思うので、後日またやる事があるなら、再評価したいと思う。カードは日本語化した方が良さそうだ。ちょっと解りにくいのがプレイテンポを下げたのかも知れない。
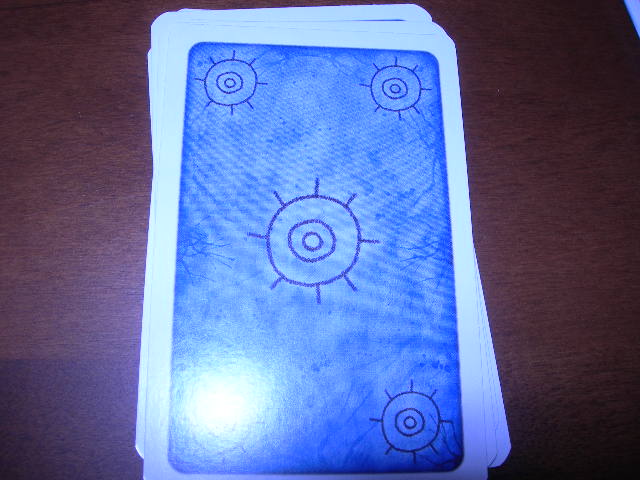
ん? よく見りゃこのカード…いやあ、中学校の頃、よくこんな落書きしたわw
再プレイにて
ブルームサービスがあまりにもおもしろかったので、当時、やってそんなに面白かった印象がなかったカードゲーム版をmiaとコタと3人でやってみることにした。せっかくなんでTAMから貰った和訳シールをポチポチと貼った。
と、その前に、なんとなくTwitterで調べたら、こんな事が書かれていた。
メビウス訳では【アクション】【支持】だが、そもそもそういうニュアンスではなく【我こそは○○である!】【そうかもね!】らしい。ドイツ語で字が小さかったから、気にもとめなかったが、確かにそんな風に書かれている。
やってみると
わし「我こそは、魔女である!」
mia「うーん、そうかもね!」
コタ「いやいや、ぼくこそ魔女だよ!
_| ̄|○ il||li
こういうやりとりはこのゲームに見事にマッチしていた。
ブルームサービスと違い、3人でやってもノンプレイヤーはいないので、バッティングが少なくなる。そしてテンポが非常に良くなってめちゃめちゃおもろかった。
最初にやったとき、ゲーム初心者を混ぜて長考されてたので評価が低くなったのかもしれない。どうにもわしは長考されるとだれてしまってあかんわ。テンポよくやれば5人でもやはり楽しいだろう。(わしが)
ブルームサービスからすると単純なゲームだが、単純だからといってつまらなくならないのがゲームの奇妙な点である。これは評価を無印から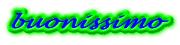 に改めたい。お手軽さという点では明らかにこっちが勝っており、mia曰く、こっちの方が好みで楽しいとの事だった。
に改めたい。お手軽さという点では明らかにこっちが勝っており、mia曰く、こっちの方が好みで楽しいとの事だった。