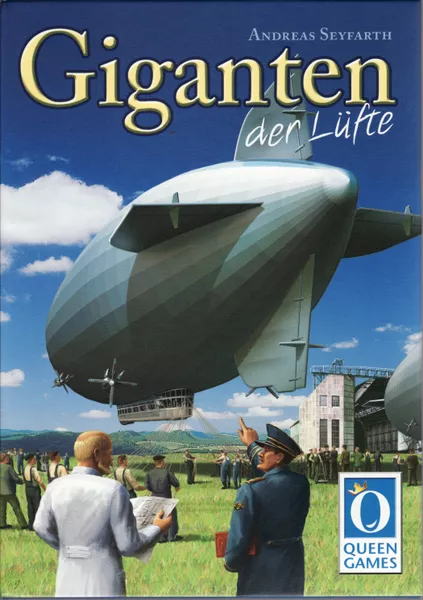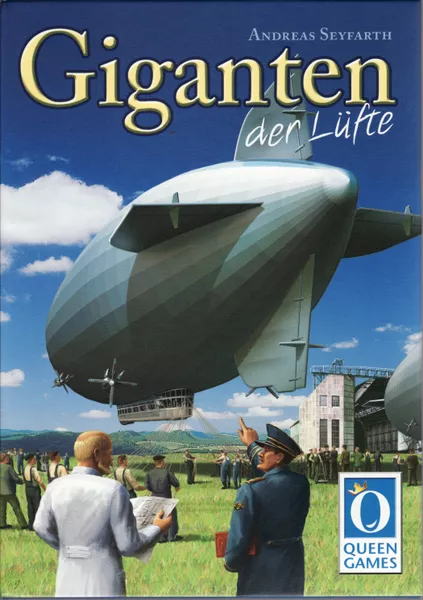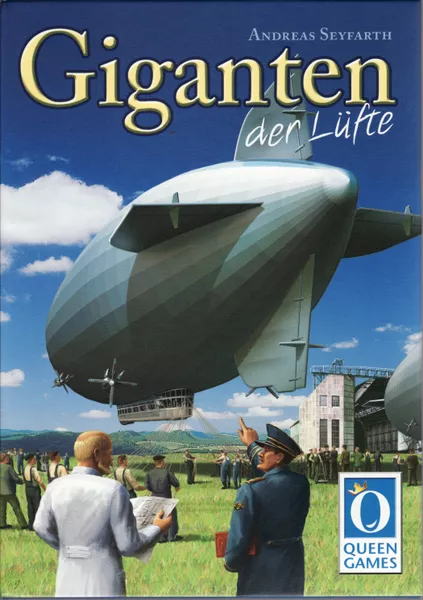 |
Andreas Seyfarth
|
Queen Games
|
2〜4人
45分
|
天空の巨人
空を飛ぶ豪華客船
それは1936年に完成しヒンデンブルグ号と名付けられ世界への旅に出かけた。
プレイヤーはこの大型硬式飛行船の開発にしのぎを削ることになる。
プレイ感
ファミリーインクが欲しくて、ついでにやっても良さそうなものを物色してて購入したのがこれ。まあ、失礼な言い方やけど、王への請願のサイコロシステムを使ったゲームで、わしは王への請願がいまひとつ面白くなかったのだ。色々と改変されてるとあったので、そこはザイファルトのお手並み拝見ということで。ヒンデンブルグ号の開発というテーマは結構好きである。
飛行船カードを色ごとに分けて、4つのマスに下から濃い、普通、薄い色順に積み重ねる。後半になると勝利点が高いカードがでる寸法だ。
開発カードを濃い色の上に時代タイルを置き、その上に普通の色、薄い色と積み重ねる。
各自個人ボードと事業タイル、ボーナスチップを持ち、上から開発カードを1枚ずつ配り、ボードに配置する。それから、場に6枚引いて色に合わせて置いておく。
スタートプレイヤーはボーナスチップを3枚、その他は4枚、ボードに置き、残りは横にのけておく。
セットアップはかなり楽ちんである。

飛行船カードは3枚ずつの4箇所の山になる。上にある巨大なのがヒンデンブルグ号で、2種類の勝利点が描かれている。巨大なヒンデンブルグ号の駒もある。
手番は、開発カードを1枚引いて場におく。それから、自分が欲しいカードを宣言して、個人ボードのカードから使えるサイコロを振る。最初は事業タイルと、初期カードで白サイコロが2個振れる状態の筈だ。
サイコロは白、赤、黒とそれぞれ3個ずつあり、順番に目が大きくなっている。例えば白は3が最高だが、黒は8が最高だ。サイコロは各色3個までしか振ることができない。

わしはイタリアの開発チームを率いる。左上が事業タイルで白サイコロ1個描かれており、最初に貰った開発カードからも白サイコロが1個描かれている。つまりこの状態やと白サイコロ2個振れるということだ。
開発カードは紫、茶、橙、黄、青、緑とそれぞれの分野に分かれており、1枚しか保持できない。
そうなると黒が一番良いやんとなるのだが、そこは考えられていて、手に入るカードでどのサイコロを使えるかが指定されてる。例えば白白5と指定されたカードがあれば、白サイコロ2個の合計値で5以上出せばゲットできるということだ。当然3個振れる(そのうち2個を選択)と確率は高くなる。
カードは王への請願と違って、全部、サイコロの合計値となってるので分かりやすい。
もし数字が足りなければ、ボーナスチップを1枚のみ支払うことでさいの目に+1できる。開発失敗すればボーナスチップを1枚貰う。また3枚ボーナスチップを支払うことで手番をもう1度できる。
開発カードは、6種類に分かれていて、資金はサイコロ追加、技術者はサイコロの目固定、材料はサイコロのグレードアップといった感じでそれぞれ効果が違っている。これらのカードは常に1枚ずつしか持てないので、同じ開発カードを手に入れたら前のは捨てる必要がある。
飛行船カードは全部、勝利点のカードで、一番上のものしか開発できない。ある山が全てなくなると、ヒンデンブルグ号を開発できる。やり方は同様だが、成功すると手元のボーナスチップを裏向けに配置する。手元になければ、ストックから配置する。またヒンデンブルグ号の巨大な駒を貰える。これはさいの目に+1できる駒だ。誰かがヒンデンブルグ号開発すれば移動する。

最初に欲しいカードを指定する。それから左上に書いてあるサイコロの合計値が右の数字以上であれば成功だ。
例えば右下に見えるエンジンは白1赤1の合計で7以上あればいい。白サイコロを2個と赤サイコロを2個振ったとしてもどちらも1個ずつを選び合算するのだ。
ヒンデンブルグ号をすべて開発するか、飛行船カードの山がそれぞれ1枚以下になったら終わりだ。得点は手に入れたカードの勝利点と、ヒンデンブルグ号は開発仕切っていれば高得点の方を、開発途中なら低い方の得点となる。
というわけでゲームスタート
最初は適当に開発者カードを選んでいく。
はたと気づく
わし「え、これ白、1〜3までしかでぇへんやん!」
というのをオール1を出したりしておかしいなと思ってようやく知るといういい加減さ。
ならば、とりあえず白より赤、赤より黒やろということで、白3を赤2に変更できる素材カードに交換した。
数字はなかなか思ったようにでないので、科学者の固定の目がでているのがとても欲しい。これは追加でさいころが振られている状態なのだ。
そうこうしているうちにあっという間に、時代が2の時代になった。事業タイルをひっくり返し、赤さいころも追加で使えるようになる。ここからが本番だ。

第2世代になると事業タイルをひっくり返す。白と赤サイコロが1個ずつ使えるようになる。
mia「これ、勝利点ついてるんだけど、同じのを手に入れたら捨てないといけないの?」
わし「そうや」
と何度言うてもしつこく訊いてきてルールまで開こうとするので段々とむかついて険悪なムードになってきた。
mia「せっかく勝利点ついてるの捨てるなんておかしいじゃないの」
開発カードには勝利点がついてるものがあり、ぎゃあぎゃあ抜かしてるがそこは取捨選択していく必要があるのだ。
なんだかんだ言いながら、miaは結構上手いこと飛行船開発まで行って勝利点を稼ぐ。
そこで気づく。
わし「あれ、これ、白サイコロ必要なんじゃ?」
飛行船カードは一番上は白サイコロだけで手に入れるものばかりだ。そんなんを無視して強かろうと赤サイコロや黒サイコロにしてしまうと目も当てられないことになる。開発カードはギリギリになるように出来ていて、赤や黒を増やそうとするとどうしても白さいころが少なくなるようになってるのだ。

科学者は固定の目を持ってるものが多い。エンジンは、さいの目にプラス修正するものが多く、素材はさいころの交換が多いといった感じで特徴がある。
つまり、時代時代に応じて、持ちサイコロを変化させていく必要があったのだ。
1箇所の山をmiaとそーじろが攻めてたおかげで、ヒンデンブルグ号が開発可能になった。
ヒンデンブルグ号は赤サイコロをよく使うので、わしも開発に参加できるようになった。
わし「ヒンデンブルグを開発する」
この頃にはリストラも進んでおり、赤さいころ4固定を持つ科学者をやとっていた。
そして、成功する。
ヒンデンブルグ号の駒をゲットしたと思ったらmiaもすぐにヒンデンブルグの開発を成功させて、一度も使わずに駒を取られてしまった。

1箇所の飛行船カードだけが一気に開発されたので、そのままヒンデンブルグ号が開発可能になった。
そうなるとわしはかなり厳しい。
miaは白さいころ軍団をやたらと残しているので、飛行船カードを次々に開発し、いつの間にか1枚以下になってゲーム終了。
miaのぶっちぎりの勝利だった。

すぐにヒンデンブルグ号をmiaに取られてしまった。
所要時間60分
miaともめたのと長考のおかげで長くなってしまった。
そーじろが考えすぎと急がせてた。
これ、もっかいやらんと評価できひんなということで、翌々日再戦することになった。
なんせすぐに赤とか黒に替えたらあかん。その都度タイミングをみて開発をしていく必要があるのだ。
2回目は順序立ててじっくりとリソースを確保していく。
全員、白サイコロが潤沢なうちに飛行船を開発していく。そして2枚目が現れた時に、一斉に赤サイコロに変更していく。そーじろが一歩抜きん出て早めに赤サイコロで開発を決めてきた。
わしはその先を見越して黒サイコロも振れるように準備していた。
ところが、これをぶちやぶるそーじろの速攻戦術が炸裂する。
あまりにも満遍なく飛行船カードを手に入れたもんやから、残り1枚を作ることでゲームが終了する状態となったのだ。
そしてそーじろはそれを見越して、さいころを振る。
そーじろ「やったやった。成功」
なんと、飛行船の山が全部きっかり1枚だけ残ってゲーム終了。
となると、最後に得点を入れたのが勝つのは、冷たい料理の熱い戦いのロブスター手に入れたら勝ちと同じ現象となる。最後に点入れたら強いのだ。
実は一番開発が遅れてたそーじろが1点差で勝利した。
所要時間25分
mia「はやっ!」
ヒンデンブルグ号のヒも出んうちに終わってしまった。めっちゃストレス。わしが手に入れた黒サイコロどないすんねん。
(|| ゜Д゜)ガーン!!
すぐ終わったんで、もっかいやろうということになった。
今度は、ヒンデンブルグ号の最終開発まで進んだが、これまたそーじろの勝利となった。なんか勝てんわ。
ソマーリオ
ただのサイコロゲームと思いきや、そこらへんはザイファルトはよう考えてた。こういった開発ゲームは、ひたすら積み重ねていけばいいというのが多いが、これは時代によって途中で変化させていく必要があるというのがよく出来ている。
基本的に3つのさいころを使うだけなので、自社の開発力をあげて差別化するという感じは薄くなってしまったが、その制限はゲームとしてはよく考えられている。
このゲームは見極めが大事だ。
王への請願とは違って、成功はただの合計値だけなので、初見であってもカード効果を知り尽くす必要はなく見通しはとても良い。今、どのさいころが何個振れるかというのが素材のさいころ交換のおかげで少しわかりにくくなっている。
こうしてみると思ったよりも考えるところがあり、悪くはないのだが、プレイ後の満足感というのがあまり高くない。ヒンデンブルグ号の開発前に終わってしまう勝利条件を抜きにしてもゲームやったった感が薄いのだ。つまり速攻で終わった2回目はえ、もう終わり? って感じだった。
プレイ感が軽いので、さっと出してやるのはいいと思うが、なんかもう少し重めの要素があった方が好みではあった。
それにしてもヒンデンブルグ号開発やのに、イタリア、フランス、アメリカ、オランダというのがどういうこっちゃ?? あ、あと一つ注文つけるとすれば、どのカードを選んだかマーキングする駒が欲しかった。おはじきで代用した。
4人プレイにて
その後、コタを交えて4人プレイをした。どうにもコタは戦国時代のようにサイコロで何かをしていくゲームというのが好きなようだ。
リクエストが多くかれこれ2,3日の間に5回ほどプレイしているが、感じたのはヒンデンブルグみたいなしんどい開発をせずとも、勝利点付きの開発カードで勝った方がいいんじゃないか。終了条件がゆるいおかげでヒンデンブルグを最後まで開発することは、速攻プレイヤーがいるとほとんど無理である。
勝利点の高い開発カードで補った方が強いんじゃないかという戦法はコタが編み出してぶっちぎった。全員がそれを抑えればまた展開は変わってくるのかもしれないが、相手の状況をよく判断する必要がある。
コタはボードゲームで偏った変な戦術を取ることがよくある。宝石の煌きでも、最初から3のカードばかり狙ってくる。わしはゲームのバグなんじゃないかと思えるが、そこにはまれば強いのだが、はまらなければ全然あかんのだ。例えばこの天空の巨人と宝石の煌きではかなり強いんじゃないかと思えたが、アルナックではひたすらコンパスを集めるプレイをしたがまったくあかんかって、このゲームが好きじゃないようだ。うちのお父んに似てるかも。
ただテーマ的にやはりヒンデンブルグを開発したいので、終了条件を変えるというローカルルールを作ってもいいかもしれない。